小川未明文学賞にご応募いただいた639編(短編作品352編、長編作品287編)について、令和7年2月12日(水曜日)に最終選考会を行い、下記のとおり大賞と優秀賞が決定しました。

作品名:「ほーちゃんと、旅に出る」(長編作品)
作者:黒田 季菜子(くろだ きなこ)(46歳 大阪府在住 主婦)
賞金:100万円
記念品:「小川未明童話全集」(全16巻 別巻1 大空社)
大賞受賞作は単行本として株式会社Gakkenから令和7年11月頃に刊行予定。
小学5年生の金澤伊吹には、ひとつ年上の兄、穂高がいる。みんなからほーちゃんと呼ばれている穂高は、普通の会話が成り立たず、突然に走り出したり、大声で叫んだりする。伊吹はそんな兄のことが全く理解できなかったが、少しずつ受け取り方が変わっていく。
9月の末、ほーちゃんは風邪で修学旅行を欠席する。そのことを「かわいそうや」と言い出したほーちゃんの支援員のトモさんは、勝手にほーちゃんを旅行に連れていく計画を立てる。気がすすまないまま旅行に巻き込まれた伊吹は、じいちゃんや「コバトハウス」の人々、難しい病気を持つ同級生のコトコと共に、旅行の準備を進める。
このたびは第33回小川未明文学賞の大賞に選出していただきまして、本当にありがとうございます。
「ほーちゃんと、旅に出る」の登場人物、ほーちゃんの妹の伊吹は予測のつかない兄の行動に翻弄される日々にやや辟易しています。介助者なしに外出や食事のできないマコトさんは、介助を受けてもそれは自分の権利だから「ありがとう」なんて言わないと言います、ほーちゃんは、自分のことを何も話してくれません。
それぞれにそれぞれの考えと立場と主張があります、誰も間違っていない。そういう人達がみんなで集まってひとつのことをしようとしたら、やっぱり大変かしら。そう考えながら去年の夏、パソコンのキイをパタパタ叩き続けました。
ここ数年「多様性」という言葉をよく聞くようになりました。「色々な人達が互いを認めて共存してゆく」という意味のそれが、未来を生きる子ども達にとって更に優しい香りする、善いものを指す言葉になるといいなと思って書いたのが、この「ほーちゃんと、旅に出る」と言ってしまうと、少し大げさかもしれませんが。
さて、ほーちゃん達の旅が、果たして善いものになったのか、それは書き手のわたしにもわかりません。ただこうして大賞に選んでいただいて、ほーちゃん達が本当に広い世界に旅に出ることになったことが、今、本当に嬉しいです。

作品名:「まねき猫よろず相談所」(長編作品)
作者:岩田 早苗(いわた さなえ)(60歳 東京都在住 学童保育指導員)
賞金:20万円
記念品:「限定本 眠い町」(DVD付、架空社)
ある神社のかたすみに、まねき猫の相談所がある。相談所を開いたのは、あねご肌の猫の「リリー」、聞き上手なオスのミケ猫の「こたつ」、そしておしゃべりな「あか助」の3匹。なかでもこたつには、それぞれのまねき猫が持つ福を招く力を測る能力があった。
あか助の作ったチラシを見て最初に相談所にやってきたまねき猫の「豆太郎」は、自分が今の主人の元に来て以来、主人が不幸になっていると言う。こたつたちは豆太郎に寄り添い、逆転の発想で解決策を考える。
その後も悩みを抱えたまねき猫たちが次々に相談所にやってくる。まねき猫たちの悩みを聞く中で、こたつは自分がまねき猫たちのためにできることは何か考えるようになる。
両親は横浜で中華料理店を営んでいました。二人とも大変な働き者で、私は数えるほどしか家族揃ってゆっくりと食事をしたことがありません。そしてその店のショーウィンドウには、ぼってりとした大きなまねき猫がいて、やはり休みなくお客さんを招いてくれていました。人にはそれぞれ違った悩みや苦労があるように、まねき猫にだって置かれているお店によって、違った悩みや苦労があるはず、そう思ったのがきっかけでこの物語は生まれました。まねき猫は、お店を繁盛させるために一緒に働く、いわゆる同志のような存在なのではないでしょうか。私の両親の店を繁盛させてくれたあのまねき猫への感謝を込めて、この作品を贈りたいと思います。
さて私は生まれも育ちも横浜ですが、父の故郷が新潟だったため、深いご縁を感じています。小学生の頃は夏休みのほとんどを米農家である伯父の家で過ごしていました。豊かな自然に囲まれた夢のような毎日でした。どじょうやメダカを捕まえて、ホタルの美しさに心を奪われました。これらのことは全て私の創作の原点となっています。今回、上越の地でこのような小川未明文学賞という素晴らしい賞をいただくことになり感慨もひとしおです。本当にありがとうございました。
1次、2次の予選を経て最終選考に残った受賞作以外(大賞・優秀賞受賞作を除く)の作品は次の7編です。

(注)番号は受付順です。敬称略。
今井恭子、小川英晴、小埜裕二、柏葉幸子、矢崎節夫、株式会社Gakken 児童読み物チーム 編集長
(注)敬称略
今回の最終候補作は優劣つけがたく、たいへん迷いました。大賞となった「ほーちゃんと、旅に出る」は、障害者たちと支援する人々を明るく描いた心温まる作品でしたが、登場人物全員があまりに善人過ぎて、こんな風に物事は楽観的に進まないのではという疑問を抱きます。登場人物が多く煩雑になったのと、長文が多いのも気になりました。
「まねき猫よろず相談所」は、今回一番面白く読みました。存在しなくていいまねき猫はいない、というテーマはそのまま人間社会に当てはまります。ストーリーも良くできており、言葉遊びもたくみで軽妙な文体。しかし、ちょっと作り過ぎた印象が強いです。
「時をこえる時計屋 刻刻堂」はタイムリープできる時計にまつわる物語でしたが、2人の少年が不思議な時計で救われるエピソードまではすんなり読めたものの、その謎解きとなる最後のエピソードは、余りに壮大に作り過ぎた感がありました。
私は「ヒキガエルの夜」のシンプルなストーリー、映像が鮮やかに浮かび上がる文体に最もひかれましたが、オーソドックス過ぎて新鮮味には欠けたかもしれません。兄にはヒキガエルという守り神がいましたが、弟にはいないのか、また弟のその後が気になります。
「ヨーソロ 」は東日本大震災で自宅に住めなくなり、祖母の実家だった山の中の古民家に移り住む少年にまつわる物語です。漁師だった祖父のように、何度でもやりなおそうと気づくまでを描いていますが、情報量が多過ぎ、混乱が見られました。
」は東日本大震災で自宅に住めなくなり、祖母の実家だった山の中の古民家に移り住む少年にまつわる物語です。漁師だった祖父のように、何度でもやりなおそうと気づくまでを描いていますが、情報量が多過ぎ、混乱が見られました。
今回の選考では、長編にすぐれた作品が多く、私は鍵頭なるAIが登場する「時をこえる時計屋 刻刻堂」をつよく推した。この作品は、時を止める、過去に行く。未来の自分へのメッセージの三つの章から成り立っていて、特に時計屋の店員である鍵頭の存在が不思議なリアリティを持って迫ってくる。力のある作家だと思う。また「刻刻堂」という店名もよい。
次に私は「ほーちゃんと、旅に出る」に注目した。登場人物は多いが、ひとりひとりが個性豊かに、かつ生き生きと描かれていることに好感を持った。生きていくことで人は様々な問題に直面するが、それをつねに前向きに解決していく姿勢はよい。ただし、ここに登場する人が、すべて善意の人たちで成り立っていることが気になった。現実には差別意識を持った人もいるはずだし、それらをも含めて、現状を解決してゆくことが重要ではないかと思った。
「ヒキガエルの夜」は、登場人物は兄と弟、父と母とおじさん、それに二胡の先生たちだが、登場人物をしぼったことで、大変読みやすく、情景が目の前に浮かぶように描くその手腕に魅了された。しかし、一方で、誰もが考える解決方法によって書かれた作品であることも同時に感じた。
「まねき猫よろず相談所」は今回の全作品中、最も作者の実力を感じさせる作品であった。読み物としては申し分ない。ただし、五つの章から成り立っているのだが、長い。もっとコンパクトにまとめてくれれば、さらに評価はあがっただろう。まねき猫をテーマにしてよくここまで書き込んだとも思うが、もう少し、立ち止まったり、振り返ったり、読者に考えさせる場面があってもよかったのではないか。
最後に短編についてだが、児童小説を短くしたのが短編ではない。かつての童話のように、複雑な時代状況のなかから、ひとつの真理を知り、純一な思いを積み上げ、それを象徴化して表現するのが、私の望む短編である。ぜひ、黄金期の童話を参考にして頂ければと思う。
今回、短編部門3編、長編部門6編が最終選考の対象となった。短編では「ありがとー」が子どもの恥じらいと思いやりを鮮やかに切り取っていて好ましかった。「袖引小僧」は優しさにあふれ、「カモシカのゆうびんやさん」は展開が巧みであったが、語り過ぎたり急ぎ過ぎたりした。長編は選考委員の間で評価が分かれた。それは今回の長編応募作が、テーマが異なっても、優劣つけがたい、ともに踊る姿を見せていたからであろう。私は「ヨーソロ 」を一押しした。感動が大きく、子どもたちに読んでもらいたい作品であった。震災を語ることの難しさを作者は承知していた。次に「夏服に着替えたら」を押した。小学校中学年の女の子の成長過程にともなう気持ちの変化が身体感覚とともに描かれていた。「ヒキガエルの夜」はイメージ喚起力のある作品だが、不条理を不条理と捉える目が欲しかった。「まねき猫よろず相談所」「ほーちゃんと、旅に出る」「時をこえる時計屋 刻刻堂」が選考委員の間で総合的に評価が高かった。「まねき猫よろず相談所」は手慣れた筆運びで物語を読む楽しさがあった。未明童話の設定やテーマが意識された作品だが、最後の章の収め方が気になった。「時をこえる時計屋 刻刻堂」は作者の筆力に舌をまいた。この童話は今の子どもたちには理解されても、大人には無理かもしれない。私は小学4年生の平凡な巻始(まき はじめ)の生き方を語る作者の姿勢に好感をもった。「ほーちゃんと、旅に出る」は、障害をもつ人とその人をとりまく人々の物語である。スピード感があり、エピソードは多いが、それぞれの話は、子どもを事故で亡くした2人の父親の哀しみを基底に沈めることで、相手のことを思いやる優しさや、ある種の縁のようなつながりを理解させる作品となっている。「ほーちゃんと、旅にでる」が大賞となり、「まねき猫よろず相談所」が優秀賞となった。異存はない。「ヨーソロ
」を一押しした。感動が大きく、子どもたちに読んでもらいたい作品であった。震災を語ることの難しさを作者は承知していた。次に「夏服に着替えたら」を押した。小学校中学年の女の子の成長過程にともなう気持ちの変化が身体感覚とともに描かれていた。「ヒキガエルの夜」はイメージ喚起力のある作品だが、不条理を不条理と捉える目が欲しかった。「まねき猫よろず相談所」「ほーちゃんと、旅に出る」「時をこえる時計屋 刻刻堂」が選考委員の間で総合的に評価が高かった。「まねき猫よろず相談所」は手慣れた筆運びで物語を読む楽しさがあった。未明童話の設定やテーマが意識された作品だが、最後の章の収め方が気になった。「時をこえる時計屋 刻刻堂」は作者の筆力に舌をまいた。この童話は今の子どもたちには理解されても、大人には無理かもしれない。私は小学4年生の平凡な巻始(まき はじめ)の生き方を語る作者の姿勢に好感をもった。「ほーちゃんと、旅に出る」は、障害をもつ人とその人をとりまく人々の物語である。スピード感があり、エピソードは多いが、それぞれの話は、子どもを事故で亡くした2人の父親の哀しみを基底に沈めることで、相手のことを思いやる優しさや、ある種の縁のようなつながりを理解させる作品となっている。「ほーちゃんと、旅にでる」が大賞となり、「まねき猫よろず相談所」が優秀賞となった。異存はない。「ヨーソロ 」「時をこえる時計屋 刻刻堂」の作者の次回作を期待したい。
」「時をこえる時計屋 刻刻堂」の作者の次回作を期待したい。
今回は「まねき猫よろず相談所」「ほーちゃんと、旅に出る」「時をこえる時計屋 刻刻堂」の3作が同点という評価を得た。3作とも書きなれた文章で読みやすく、楽しめる作品だった。また、それぞれにいいところもあれば、欠点もあったと思う。その中で、大賞は「ほーちゃんと、旅に出る」、優秀賞は「まねき猫よろず相談所」と決まった。
「ほーちゃんと、旅に出る」は、一番読後感がよかった。旅に出るんだというわくわく感が伝わってきた。登場人物が個性的で魅力的だった。その分、辛い所には目をつぶっていい人ばっかり出てきたのかと思える。障害のある兄を持つ妹の思いはあまりに大人だ。同じことは「夏服に着がえたら」や「ヨーソロ 」にも言える。奇声を発して走る兄のことをバカにしたり、傷跡に意地悪なことを言う子も、まだ被災者をいじめる子もいると思う。そこは書かれていないことが気になった。「ヨーソロ
」にも言える。奇声を発して走る兄のことをバカにしたり、傷跡に意地悪なことを言う子も、まだ被災者をいじめる子もいると思う。そこは書かれていないことが気になった。「ヨーソロ 」は被災地のその後というテーマはよかったと思う。
」は被災地のその後というテーマはよかったと思う。
「まねき猫よろず相談所」は、個性的な猫が出てきて楽しく読めた。5個のパートに分かれていたが、それぞれあきさせなかった。ここまで書けるのだから一つの大きな山がある筋立てにして欲しかったと思う。
「時をこえる時計屋 刻刻堂」は、さあ、どうなる という読者の疑問をさそう筋立てだが、その疑問を解決する時を操作する理屈が簡単には伝わってこない。少しお説教くさくなった。
という読者の疑問をさそう筋立てだが、その疑問を解決する時を操作する理屈が簡単には伝わってこない。少しお説教くさくなった。
あまりが評価なくて残念だったのが「ありがとー」だ。この枚数で孫の祖父に対する思いがリアルに伝わってきたと思う。やさしい物語だった。
初めて選考に関わらせてもらい、9編の作品を読ませていただいたが、さすがに600編を越える中から選ばれて残った作品だと感心させられた。短編が3編あって、その中では「ありがとー」のおじいちゃんと主人公のゆうくんの繋がりのあたたかさに心引かれた。
残りの6編が100枚前後の長編で、それぞれにすぐれていていいと思った。「夏服に着がえたら」は小学1年の時、やけどをした智子が4年生になってもらった「プール授業のお知らせ」で、今年も中耳炎と嘘を母親に書いてもらって休もうとする。その時、学級委員の男の子にある本を勧められ、その本を読んで大きな心の変化が訪れることになる話だ。いつかこの作品がより深く育って、今、同じように思いがけず傷をおってしまつた子が、この作品に出合ってくれたらいいなと思った。
「時をこえる時計屋 刻刻堂」は書きなれていて、物語の進め方も上手で読ませられたが、後半の種明かしが先にわかってしまったようで、もったいなかった。
「ほーちゃんと、旅に出る」は「普通ってどんなこと」「できるひとができることをしたらええんや」と、セリフのひとつひとつが読み手に考えさせる力があった。ほーちゃんの妹の伊吹の前向きな姿に読み手として心を楽にしてもらった。旅に出るだから、出る前まででいいのだけれど、旅に出ているほーちゃんとみんなの姿が見たい気がした。
「まねき猫よろず相談所」は今回の中では、私としては一番、読み物としておもしろく読めた。作者の今後に期待したい。
「ヒキガエルの夜」は、二胡の音が聴こえてきて、中国の風景が広がってきて上手かった。
今回は長編2編が受賞されたが、短編でも長編を超える作品がでてくるといいなと、選考をさせてもらって深く思った。9編の作者に、すぐれた作品を読ませていただいて楽しい時間に感謝
最終選考作品は、長編6点、短編3点、テーマは各々だが、いずれも文章レベルの高さを感じた。大賞「ほーちゃんと、旅に出る」は、兄に対しての感情や気づきが、主人公の素直な視点でよく描かれている。同級生と友情を深めていく流れも自然。旅前の話が面白いため、出発後の物語も読みたいと感じた。優秀賞「まねき猫よろず相談所」は、猫、まねき猫同士の交流が大変楽しく読み進められる。一方で登場するキャラクター含めて諸々の設定が掘り下げられていると、深みが増したように思う。「ヨーソロ 」は、震災を経た家族の絆が丁寧に描かれている。「前向きに」というメッセージが、具体的なエピソードをもって主人公の自然な感情変化で表現されていると尚よかった。「時をこえる時計屋 刻刻堂」は非常に工夫を凝らされたタイムリープの話。命の描写に関しては慎重であってほしいのと、3話目が説明的である点が惜しい。「カモシカのゆうびんやさん」は文章表現が巧みであるが、この話の主軸の一つであるクラスメイトとの問題が解決されてほしかった。「ありがとー」は、人となりや感情の動きが自然な過程をもって描かれているとよかった。文章が整っていて読みやすい。「袖引小僧」は、友だち、自分の感情について少しずつ知っていく過程が優しく描かれている。終わり方により、本筋が見えにくくなってしまった印象を受ける。「夏服に着がえたら」は、人と違う見た目を隠さなくてもいいという話だが、様々なケース、立場も含ませられるとよかったか。まわりの登場人物の人柄がよく、ほっとする。「ヒキガエルの夜」は、中国の風景が目に浮かぶようで美しい作品だった。やや既視感のある展開なので、そこにオリジナル性があると作品として個性が増したと思う。
」は、震災を経た家族の絆が丁寧に描かれている。「前向きに」というメッセージが、具体的なエピソードをもって主人公の自然な感情変化で表現されていると尚よかった。「時をこえる時計屋 刻刻堂」は非常に工夫を凝らされたタイムリープの話。命の描写に関しては慎重であってほしいのと、3話目が説明的である点が惜しい。「カモシカのゆうびんやさん」は文章表現が巧みであるが、この話の主軸の一つであるクラスメイトとの問題が解決されてほしかった。「ありがとー」は、人となりや感情の動きが自然な過程をもって描かれているとよかった。文章が整っていて読みやすい。「袖引小僧」は、友だち、自分の感情について少しずつ知っていく過程が優しく描かれている。終わり方により、本筋が見えにくくなってしまった印象を受ける。「夏服に着がえたら」は、人と違う見た目を隠さなくてもいいという話だが、様々なケース、立場も含ませられるとよかったか。まわりの登場人物の人柄がよく、ほっとする。「ヒキガエルの夜」は、中国の風景が目に浮かぶようで美しい作品だった。やや既視感のある展開なので、そこにオリジナル性があると作品として個性が増したと思う。
今後も今、そしてこれからを生きる子どもたちに向けた新しい作品を期待したい。
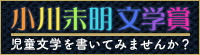 <外部リンク>
<外部リンク>