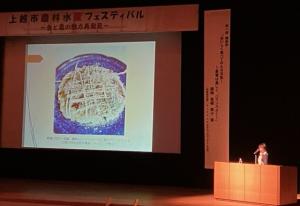令和4年10月29日(土曜日)に行われた「食育実践セミナー」の食育講演会や展示の内容を「食育実践セミナー(WEB版)」として紹介します。
家族や自分の食生活を改めて見直し、食育の実践につながるヒントとなる内容ですので、是非ご覧ください。
- 食育講演会
- 食育の展示
「おいしく食べてみんな元気 食事は楽しく、バランスよく」
- 「食育」とは
- 子どもたちに正しい食生活を身に付けさせるには
- 時短料理を教えます
- お米を食べよう
- 上越の野菜
- レシピ紹介
- Q&A
講師プロフィール

- 高橋 典子 氏
- 料理研究家、おから料理研究家、「NIPPONおからプロジェクト」代表、一般社団法人シェフード女子部メンバー
- 2002年から料理教室を主宰し、さまざまなジャンルの料理やデザートの研究を続けている。栄養的にも優れた食品であるおからを、多くの方に日常の食卓で活用してもらうため、地方自治体、教育・医療施設、食品メーカー、飲食店、大学・研究機関、食関係の団体、メディアなど各分野での普及活動を精力的に行っている。
- 平成17年に食育基本法が施行された。その中で、「食育とは生きるための基本であり、知育・徳育・体育の基礎となるもの」と書かれている。あらゆる世代の国民に食育は必要であり、特に子どもたちに対する食育は大切であるとなっている。食育基本法の前文には、食育について有意義なことが書かれている。機会があればご覧いただきたい。
食育基本法 [PDFファイル/215KB]
- 上越市の学校給食の献立を拝見した。昔と今では学校給食に対する考え方が変わり、全国の食材を食べることができる。地元や季節の食材、メニュー、日本にとらわれないものも取り入れて、献立が作られている。栄養士の方は本当にすごいと感じた。
- できれば家族で買い物に行き、帰ってきたら、そのまま家族で下ごしらえをする。子どもと一緒に野菜を洗ってゆでる、電子レンジで芋を柔らかくする、容器に入れて冷蔵庫で保存することなどを家族でやっていくことで、食への学びにつながる。
- 電子レンジを活用すると本当に時短になる。
- 青菜は少し水分を加えてラップで包んで電子レンジにかける。
- 芋は適当な大きさに切り、ラップで包んで電子レンジで加熱する。
こうしたものを冷蔵庫や冷凍庫に入れておけば、次の日遅く帰ってきて食事の支度をする時間がなくても、それを温めて少し味を付けることで、おかずにすることができる。炊きたてのご飯に混ぜる、お味噌汁の具にも活用できる。買い物をした時に、下ごしらえまですることをお勧めする。
- すべて手作りにする必要はない。例えば、1品はお惣菜にする、缶詰を活用するなど、手作りにこだわりすぎると辛くなることもある。できれば地元の食材を活かして、バランスのよい食事にしていただければと思う。
- お米の消費量は、20年前と今とどのくらい違うかご存じだろうか。全国的なことだが、特に60歳代以上の高齢者は、20年前に比べて消費量が25%減っている。すべての年代で減っているが、特に高齢者が減っている。
- 最近、糖質制限という言葉を聞く。ご飯を代表とする炭水化物を減らせば、体の調子が良くなる、痩せるというものである。
- 料理教室で生徒さんたちに聞くと、ご飯や炭水化物を食べると太るという意識がある。確かに短期的な糖質制限は、効果があると言われているが、長い目で見た時に、糖質制限は体に悪影響を及ぼすことが分かってきている。
- 一方で、お米を多くとっている男性のほうが、心臓病になるリスクが2割以上低くなっているという研究結果がある。
- また、日本人が摂っているタンパク質には、植物性タンパク質と動物性タンパク質があるが、私たちがどこから一番タンパク質を摂っているかというと、普通お肉や魚、卵、大豆を考えるが、一番多いのは米なのである。
- お米には良質のタンパク質が含まれていて、肉と魚、大豆製品、乳製品、卵に分けた時にお米に含まれる割合が一番多い。お米は本当に重要なタンパク源である。
- そういったことをあまり知らないで、ご飯を食べない、おかずだけ食べるという食生活は、体にマイナスになっている。
-
お米は、
-
重要なエネルギー源になる
-
脳を動かす原動力になる
-
重要なタンパク質源であると同時に、肉や魚のタンパク質を体に取り入れる作用をする
- お昼に上越の新米をいただいた。おいしいお米を食べることを皆さんは当たり前だと思っていると思うが、精米したてのお米を毎日食べられることは、本当にうらやましい。当たり前ではなく、こんなにおいしいお米はそうそうないので、大切にたくさん食べてほしい。
- 「上越野菜」のブランド化を進めて、生産者の方が工夫されている。枝豆、ブロッコリー、カリフラワーなどを直売所で見てきたが、ブロッコリーは、本当にうらやましい品質で力があった。
- 「雪室野菜」は、電気を使わず、野菜を雪室の中で保管する方法で、野菜の糖度が上がりおいしくなる。雪国ならではの方法だと思う。
- こういったことを含め、上越の野菜を広く発信してもらえたらいいと思う。市内でも知られていないことがあると思うし、市外や東京を中心とした消費者がたくさんいる地域にぜひ情報を届けていただきたい。
レシピ一覧 [PDFファイル/667KB]
朝食にぜひ 簡単・美味しい・ヘルシーなご飯アレンジレシピ



おからパウダーで作るレンジで5分 簡単スポンジケーキ
おからパウダーとは
おからのタンパク質含有量は、100グラム当たりの絹ごし豆腐に含まれるタンパク質よりも多い。食物繊維も多く腸にも非常にいいものである。ただ、おからは腐りやすい。それを解決したのが「おからパウダー」である。
Q1.粒子の粗いおからパウダーの使い方を教えてください
A.
- 粒子の粗いものは何といっても「卯の花」。おかららしいものを作る場合は、粒子の粗いものを使うといい。おからパウダーの4倍の水を加えると元のおからの量になる。粒子が細かいものだとクリーム状のものになる。
- ケーキを作る時も粗いものだと絶対だめということではない。粗いものは少し重くなるので、今回のスポンジケーキであれば、3~5グラムを減らして作ることもできる。
- 「おからのサラダ」。ポテトサラダのじゃがいもの部分をおからパウダーにして作ることもできる。その場合は、粗いものでも細かいものでもできるが、食感が全く違うため、滑らかなものが好きな方は細かいものを、ざっくりしたものが好きな方は粗いものを使用するといい。
Q2.おからの活用方法として、おからで染めたエプロンを紹介していただいたが、食べるだけでなく、おからを活用できるものを教えてほしい
A.
- 「おからペーパー」。紙を作るには繊維が必要で、その繊維としておからを使用している。
- おから全体のうち、廃棄されるものは10%程度、30%は飼料、30%は肥料、その他商品化されたもので、食用となっているものは1%ほど。廃棄されるものを少しでも減らしたいと思い活動している。普通の紙と違い、コストがかかり5倍くらいの値段になってしまうため、コストを下げていきたい。現在、名刺や封筒の商品化が始まっている。
注)講演の内容は無断転載禁止

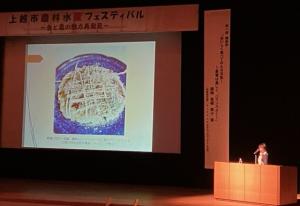
朝食ってすごい(市農政課)
勉強や運動などにおいて、朝食を食べるメリットや、「時間が無い」「食欲が無い」それぞれの人に合った朝食準備のコツを紹介します。
朝食ってすごい [PDFファイル/1.5MB]
「上越野菜」の紹介(市農村振興課)
上越市で古くから栽培されてきた「伝統野菜」と、一定の出荷量と品質を満たしている「特産野菜」を総称として16の品目を「上越野菜」として認定しています。
ご家庭でも手軽に味わっていただけるよう、「上越野菜」振興協議会がレシピ動画を作成しています。

「上越野菜」を使ったレシピ動画(外部リンク)<外部リンク>
市立保育園の給食と食育活動(市保育課)
市立保育園の給食レシピ、保育園の食育活動を紹介します。
おすすめ給食レシピ集 [PDFファイル/712KB]
市立保育園の食育活動の紹介
その他
こんな展示を行いました
我が家の食料自給率チェック(JAえちご上越地域ふれあい課)
自分の朝食のメニューがどのくらい日本で作られているかを数値で出し、日本の農業と食について、考える機会としました。

栄養成分表示と歯の健康について(上越地域振興局健康福祉環境部)
11月の「健口推進月間」に合わせた歯間ケアの周知、栄養成分表示の活用方法などの展示を行いました。

一日に食べる量について(上越市食生活改善推進員・県栄養士会上越支部)
バランスのとれた食習慣の大切さを理解し生活の中に取り入れることは、健康な身体づくりにつながり、生活習慣病の予防になります。
上越市食生活改善推進員会では、市民の食生活の実態を踏まえ、バランスのとれた食習慣の大切さをいろいろな場面で普及・啓発しています。今回の食育実践セミナーでは、大人と子供(5歳児)1日の食品の目安量を展示しました。
また、県栄養士会上越支部では、「1日に適正な栄養を摂ることで生活習慣病を予防しよう」をテーマにパネル展示を行いました。

「発酵のまち上越」の紹介(上越ものづくり振興センター)
夏は高温多湿、冬も雪により低温多湿の気候を活かし、古くから日本酒、ワインなどのお酒、味噌、醤油などの製造が盛んな「発酵のまち上越」を紹介しました。
発酵のまち上越がすごい